|
父が溜息を吐くことは、そう珍しくない。それを見るのもまた然り。 「またあの三人ですか」 それとも、は組のことですか。忍たま達が去ったあとの庭へ出て、父に問いかけた。父や土井先生が彼らのことで目一杯なことは前から知っていた。それに、自分も巻き込まれてきた。未だに彼らの扱いには慣れた気がしない。だからこそ、今日も父の脳を占めるのは彼らだと思っていた。が、口を開いた父から漏れたのは、予想外の名前。 「最近、の調子が良くないとシナ先生が嘆いておる」 知らない名前ではなかった。数少ない、よく話をするくのたまの一人だ。記憶を探ってみても、調子が悪かったり落ち込んでいたりする彼女が浮かばない。父から話を聞けば、最近の彼女はどこか上の空で実技も思うようについてこれないようだ。おかしい、先ほど会ったときは私を見つけるなり笑顔で駆け寄ってきてくれた。あれは、貼り付けられたものだろうか。乾いた笑顔だったかは、思い出すことができない。 「……少し様子を見てきますね」 「そうしてくれると助かるのう」 「父上の頼みですから」 ばれておったかい、と口角を上げる父に対して微笑みを返して背を向けた。 さて、どこへ行こうか。外にいてくれたら助かるが、教室や長屋になどいられたら様子を見ることなどできやしない。食堂に行ってみたものの、は組とくのたまのいつもの六人しかいなかったので気付かれないように逃げてきた。 ふらふらと行き場所を変えていき、たまたま見つけた体育委員の鍛錬を眺めていると視界に桃色が映った。その色の主は私が探していた本人だった。 「ちゃん」 「ん、……って利吉さん。もう帰っちゃったのかと思ってました」 返事をする彼女を見て、やっとわかった。ああ、なんだ。こんなにもわかりやすいものだったのに、気が付かなかった。彼女の表情も声色も、すべて表面だけのものだったのに。 「……最近調子が良くないんだってね」 そう私が言えば、彼女はすぐさま顔を強張らせた。唇をきゅっと結び、どこか一点を見つめている。 回りくどく、氷をすこしづつ融かしていくことだってできた。あえてそれをしなかったのは、直球で問うても同じだと予想したから。 「友達とうまくやれてないのかい」 この年頃の少女が頭を抱えることは、友人関係や自由を求めることや、少女から女性になる行為に対しての嫌悪感、この三つが多いとなんとなく知っていた。 「ううん、友達も先輩も、優しいんです」 「じゃあ、どうしてかな。私でよければ話を聞くよ」 その場に腰を降ろし、彼女にもそう促した。完璧同じ目線とまではいかないが、先ほどより高さは縮んだ。彼女は口を小さく開き、ゆっくり閉じた。言うべきか、迷っているのだろう。 「優しくて、優秀だから、少し羨ましいんです。……嘘です、結構嫉妬してます」 重々しい溜息と共に吐き出した台詞。私を合わせようとすることのない、虚ろな瞳。何か言おうと思ったが、彼女はそのまま続けた。 「みんな、恋をしている。みんなが誰かを想っているとき、わたしは技を磨いています。それなのに、わたしのほうが劣るんです。 わたしは自分の女を抑えているのに、忍としても人を越せない。 わたしに優しくしてくれる人に、苛々してしょうがないんです。だから、相談もできなくて……初めてです、人に話したの」 ぽつり、ぽつりと紡がれる言葉と、乾いた笑顔。彼女のほほを伝うのはほんの少しの涙。 「友達に対してこんなことを考える自分が嫌い、と思う自分も嫌なんです」 一度たりともこちらを見ないで彼女は言った。悪循環という泥に足を突っ込んでしまった彼女にかける言葉が何一つとて浮かばない。いつもなら、上辺だけ声を被せるのならいくらでもできる。が、それすら思い浮かばない。そんなことを投げかけたくもない。 彼女の指が湿った土の上をすべるのをぼうっと眺めながら、何もしてやれない私に、らしくもないなと心の中で自嘲した。 彼女をその泥から引き上げたいはずなのに、手を握ってやることもできない。いっその事、私に恋をしていまえばいいと思い、やっとの思いでその指に自分の指を絡ませた。 まだ、ふたりの臆病者の視線が絡むことはないだろう。 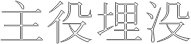 100126 |